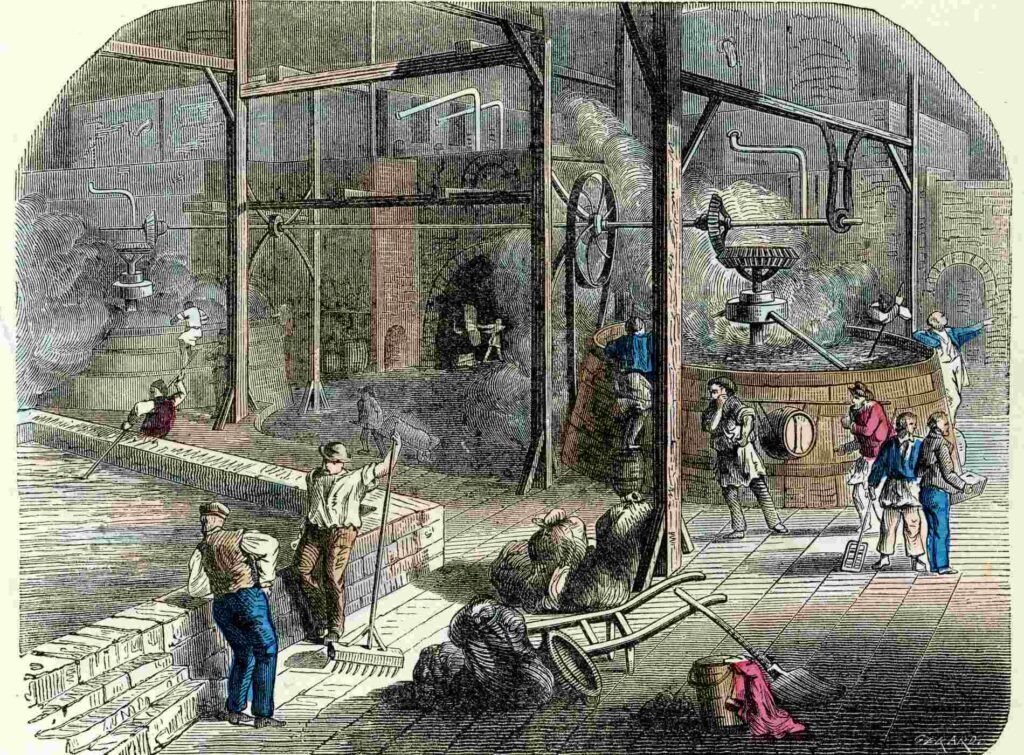BUSINESS
人手不足といわれる業界の現状とは?今すぐ必要な対策と業界別の事例

目次
人手不足の現状と対策〜業界別の実態と解決への道筋〜
現在、日本のあらゆる業界で深刻化する人手不足問題。本記事では、建設業や医療・介護、運輸・物流など、特に影響の大きい業界の実態と具体的な対応策を徹底解説します。
人手不足の背景には、少子高齢化や働き方改革による労働環境の変化があり、その解決には業界ごとの特性を踏まえたアプローチが必要です。RPAやAIの導入、働き方改革の推進、外国人材の活用など、最新の取り組み事例と共に、人手不足解消への道筋を示していきます。
経営者や人事担当者の方々に向けて、即実践可能な対策から中長期的な戦略まで、具体的なソリューションをご紹介します。
1. 人手不足問題の概要

日本の労働市場は深刻な人手不足に直面しており、2023年の有効求人倍率は1.27倍と、求人数が求職者数を大きく上回る状況が続いています。
1.1 深刻化する人手不足の実態
厚生労働省の調査によれば、全産業の約7割の企業が人手不足を課題として挙げています。特に中小企業において深刻で、中小企業庁によると、従業員規模が小さい企業ほど人手不足感が強い傾向が示されています。
1.2 地域別の人手不足状況
地域別では、労働政策研究・研修機構の統計によると以下の特徴が見られます。東京のみならず、地方でも人手不足に陥っている地域があります。
| 地域区分 | 有効求人倍率(2024年12月) |
|---|---|
| 東京都 | 1.76倍 |
| 新潟県 | 1.50倍 |
| 香川県 | 1.44倍 |
2. 人手不足の主な要因

日本における人手不足問題の根本的な要因について、主に以下の観点から詳しく見ていきましょう。
2.1 少子高齢化の影響
日本の生産年齢人口(15-64歳)は1990年の8,614万人でしたが、2020年には7,509万人まで落ち込んでいます。厚生労働省によると、2025年には75歳以上の人口が全人口の18%を超えると予測されています。
| 年 | 生産年齢人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1990年 | 8,614万人 | 12% |
| 2020年 | 7,509万人 | 29% |
| 2040年(予測) | 6,213万人 | 35% |
特に地方では、若年層の大都市圏への流出も相まって人手不足が深刻化しています。
2.2 働き方改革・労働環境の変化
労働時間の上限規制や有給休暇の取得義務化など、働き方改革関連法の施行により、企業は従来の長時間労働に依存した運営が困難になっています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、以下のような変化が加速しています:
- テレワークの普及による働き方の多様化
- 職場環境や福利厚生を重視する求職者の増加
- ワークライフバランスを重視する価値観の浸透
損保ジャパンの調査によれば、従業員の約7割が柔軟な働き方を希望しており、従来型の固定的な勤務体系では人材確保が困難になっています。
2.2.1 給与・待遇面の課題
人手不足が深刻な業界の多くは、労働時間の割に給与水準が低く、特に若手人材の確保に苦慮しています。
| 業種 | 主な給与面の課題 |
|---|---|
| 介護・福祉 | 業務の専門性・負荷に比して給与水準が低い |
| 運輸・物流 | 長時間労働の割に基本給が低い |
| 小売・サービス | 最低賃金レベルの時給が多い |
2.2.2 技能継承の問題
熟練技能者の大量退職時代を迎え、技術やノウハウの継承が円滑に進まないことも人手不足に拍車をかけています。特に製造業や建設業では、若手人材の育成が追いついていない状況です。
3. 業界別の課題と対応策

日本の労働市場において、業界ごとに異なる人手不足の課題が存在します。ここでは特に深刻な状況にある3つの業界について、具体的な課題と対応策を詳しく解説します。
3.1 建設業界の場合
建設業界では、高齢化による技能工の減少と若手人材の確保が最大の課題となっています。厚生労働省によると、平成28年の建設業の生産労働者(男)の平均年齢は44.2歳となっており、全産業や製造業に比べ、高齢化が進展しています。
| 主な課題 | 具体的な対応策 |
|---|---|
| 技能継承の遅れ | ・ベテラン技能者による若手への計画的な技術指導 ・デジタル技術を活用した技能のアーカイブ化 |
| 労働環境の改善 | ・ICT建機の導入による作業効率化 ・週休二日制の導入促進 |
| 処遇改善 | ・社会保険加入の完全実施 ・給与水準の引き上げ |
3.2 医療・介護業界の場合
医療・介護業界における人手不足は、高齢化社会の進展により需要が増加する一方で、厳しい労働条件により人材確保が困難な状況が続いています。
| 主な課題 | 具体的な対応策 |
|---|---|
| 長時間労働 | ・ICTシステムによる業務効率化 ・タスクシフティングの推進 |
| 精神的・肉体的負担 | ・介護ロボットの導入 ・パワーアシストスーツの活用 |
| キャリアパスの不明確さ | ・専門資格取得支援 ・役職・職位の明確化 |
3.3 運輸・物流業界の場合
運輸・物流業界では、eコマースの急成長に伴う配送需要の増加に対し、ドライバー不足が深刻化しています。国土交通省の報告によると、トラックドライバーの約45.2%は40-50歳となっています。
| 主な課題 | 具体的な対応策 |
|---|---|
| 長時間労働の是正 | ・配送ルート最適化システムの導入 ・荷主との待機時間短縮交渉 |
| 労働環境の改善 | ・中継輸送の導入 ・女性ドライバー向け設備整備 |
| 若手人材の確保 | ・免許取得支援制度の充実 ・給与体系の見直し |
4. 人手不足解消のための具体策

人手不足を解消するためには、複数のアプローチを組み合わせた総合的な対策が必要です。ここでは、主要な3つの観点から具体的な解決策を解説します。
4.1 テクノロジーの活用
AIやRPAなどのデジタル技術を活用することで、人手不足を補完し業務効率を大幅に向上させることが可能です。具体的な導入例として以下が挙げられます。
| テクノロジー | 主な用途 | 導入効果 |
|---|---|---|
| RPA | 定型的な事務作業の自動化 | 作業時間80%削減 |
| AI需要予測 | 人員配置の最適化 | 人件費15-20%削減 |
| 自動化設備 | 製造・物流作業の省人化 | 必要人員30-50%削減 |
4.2 働き方改革の推進
従業員が働きやすい環境を整備し、定着率を向上させることも重要な対策となります。具体的な施策として以下が挙げられます。
・フレックスタイム制やテレワークの導入
・副業・兼業の許可
・育児・介護との両立支援
・有給休暇取得の促進
これらの施策を導入した企業では、厚生労働省の調査によると働き方改革を行っている企業は離職率がそうでない企業と比較して改善したと報告されています。
4.3 採用戦略の見直し
従来の採用方法や対象を見直し、多様な人材の確保を目指すことで人手不足の解消につながります。効果的な施策として以下が考えられます。
| 採用戦略 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| シニア採用の強化 | 定年延長、再雇用制度の充実 |
| 外国人材の活用 | 特定技能制度の活用、多言語対応 |
| 兼業・副業人材の活用 | プロジェクト単位での採用 |
4.3.1 デジタル人材の育成・確保
特に注目すべき点として、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進できる人材の育成・確保が重要です。経済産業省の報告によると、2025年には最大43万人のIT人材が不足すると予測されています。
対策としては以下が挙げられます。
・社内人材のリスキリング推進
・外部研修プログラムの活用
・専門機関との連携
・ノーコードツールの導入による既存人材の活用
5. まとめ
日本の人手不足問題は、少子高齢化を主要因として深刻さを増しています。特に建設業、医療・介護、運輸・物流の分野では、事業継続に関わる重要な経営課題となっています。
この課題に対して、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAI技術の導入、省人化設備の活用が効果的な解決策の一つとなっています。また、リモートワークの導入やフレックスタイム制の活用など、柔軟な働き方の実現も人材確保に貢献しています。
採用面では、リクルートやマイナビなどの採用支援サービスを活用した効果的な求人活動に加え、シニア層や外国人材の積極的な採用も有効です。今後は、これらの対策を組み合わせながら、各企業が自社の状況に合わせた総合的な人手不足対策を実施していくことが求められます。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。
MWELT

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。