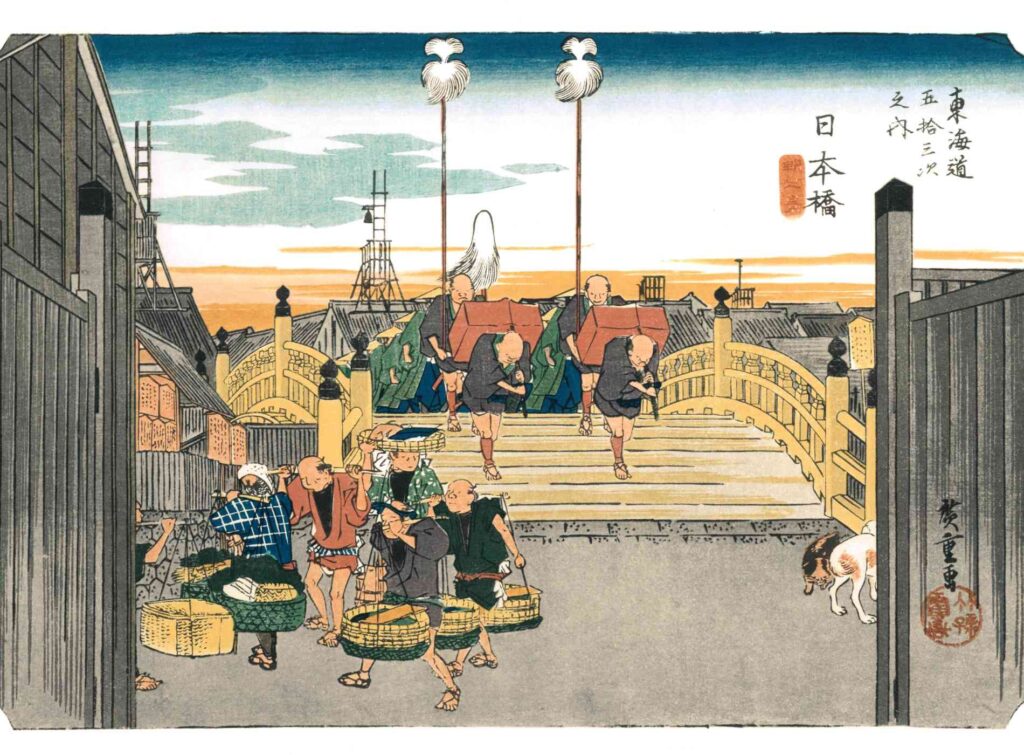BUSINESS
医療DXとは?メリット・課題から導入事例、国の取組みまで徹底解説

目次
医療DXとは何か、なぜ今注目されているのか気になっていませんか。医療DXは、単なる業務効率化に留まらず、医療の質の向上と持続可能な医療提供体制の構築に不可欠な国家戦略です。
本記事では、医療DXの定義といった基礎知識から、国が推進する「医療DX令和ビジョン2030」の全容、具体的なメリット・課題、分野別の導入事例、活用できる補助金までを網羅的に解説します。この記事を読めば、医療DXの全体像が掴めます。
▼更にDXについて詳しく知るには?
DXとはどのようなもの?導入が求められる理由やメリット・デメリットを解説
▼社内のデータをAI化するには?
ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)
1. 医療DXの基礎知識

近年、医療現場においてもデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が急務とされています。しかし、「DX」という言葉が先行し、その正確な意味や目的、なぜ今必要なのかを十分に理解できていない方も少なくありません。まずは、医療DXの最も基本的な知識から正しく理解を深めていきましょう。
1.1 医療DXの定義と目的
医療DXとは、AI(人工知能)やIoT、クラウドなどの先進的なデジタル技術を活用して、医療に関する業務プロセスやシステム、さらには医療提供体制そのものを根本的に変革し、新たな価値を創出することを指します。単にデジタルツールを導入するだけでなく、それらを活用して医療の質や患者体験を向上させ、持続可能な医療制度を構築することが最終的なゴールです。
その主な目的は、以下の3点に集約されます。
- 医療従事者の負担軽減と働き方改革の実現:煩雑な事務作業や情報共有の非効率を解消し、医師や看護師が本来の専門業務に集中できる環境を整えます。
- 医療の質の向上と個別化医療の推進:蓄積された医療データをAIなどで解析し、より精度の高い診断や治療法の選択、個々の患者に最適化された予防医療の提供を目指します。
- 患者の利便性向上と医療アクセスの改善:オンライン診療やWeb予約システムの普及により、患者の待ち時間を短縮し、地理的な制約なく質の高い医療を受けられる機会を増やします。
1.2 なぜ今、医療DXが求められるのか?3つの背景
日本が医療DXを強力に推進する背景には、避けては通れない3つの社会的な課題が存在します。
1.2.1 超高齢社会と労働力不足
日本は世界でも類を見ないスピードで超高齢社会に突入しており、医療需要は増大の一途をたどっています。一方で、生産年齢人口の減少に伴い、医師や看護師をはじめとする医療従事者の不足は深刻化しています。この「増え続ける需要」と「減り続ける供給」という構造的な課題を解決するためには、従来の労働集約的な医療提供体制には限界があります。
デジタル技術を活用して業務を効率化し、一人ひとりの医療従事者の生産性を向上させることが、医療崩壊を防ぐために不可欠なのです。
1.2.2 医療の質の向上と均てん化
都市部と地方では、アクセスできる医療サービスの質や量に大きな格差(医療格差)が生じているのが現状です。専門医の偏在により、地方では高度な医療を受けることが困難なケースも少なくありません。医療DXは、この課題解決にも貢献します。
例えば、オンライン診療や遠隔での画像診断支援システムを活用すれば、遠隔地の患者も都市部の専門医による質の高い診療を受けられるようになります。このように、どこに住んでいても一定水準の医療を受けられる「医療の均てん化」を実現するためにも、DXの推進が求められています。
1.2.3 新興感染症への対応
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、日本の医療体制が抱える脆弱性を浮き彫りにしました。医療機関の逼迫、院内感染のリスク、患者の受診控えといった問題に対し、オンライン診療や非接触型の受付・決済システム、保健所業務のデジタル化といった取り組みが有効であることが示されました。
今後起こりうる新たなパンデミックや大規模災害に備え、迅速かつ柔軟に対応できる強靭な医療提供体制を構築するため、医療情報の連携基盤の整備をはじめとするDXが急務となっています。
1.3 「IT化」「デジタル化」との違い
医療DXを理解する上で、「IT化」「デジタル化」との違いを明確に把握しておくことが重要です。これらは混同されがちですが、目指すゴールや変革の範囲が異なります。以下の表でそれぞれの違いを確認しましょう。
| 段階 | 概要 | 目的 | 医療分野での具体例 |
|---|---|---|---|
| IT化 (Digitization) |
アナログな情報をデジタルデータに置き換えること。 | 業務の省力化・効率化(部分的な改善) | 紙のカルテをスキャンしてPDFで保存する、レントゲンフィルムをデジタル画像データにする。 |
| デジタル化 (Digitalization) |
特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化すること。 | 特定の業務プロセスの効率化・自動化 | 電子カルテシステムを導入して院内の情報共有を円滑にする、Web予約システムで受付業務を自動化する。 |
| 医療DX (Digital Transformation) |
デジタル技術を前提として、医療提供体制やビジネスモデル、組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造すること。 | 新たな価値創造と持続可能な医療体制の構築 | 複数の医療機関で共有された診療データをAIが解析し、最適な治療法や新薬開発に繋げる。ウェアラブルデバイスから得られる日常の健康データを活用し、予防医療サービスを提供する。 |
このように、IT化やデジタル化は医療DXを実現するための手段であり、それ自体が目的ではありません。医療DXは、これらの技術的な基盤の上に、医療のあり方そのものをより良い方向へ変革していく、より大きな概念なのです。
2. 厚生労働省が推進する「医療DX令和ビジョン2030」とは
政府は、医療分野における情報の効果的な活用と質の高い医療の実現を目指し、「医療DX令和ビジョン2030」を掲げています。これは、2022年5月の自由民主党による提言を受け、2023年6月2日に「医療DXの推進に関する工程表」として閣議決定された、日本の医療DXにおける羅針盤となるものです。このビジョンは、国民一人ひとりが生涯を通じてより良い医療を受けられる社会を構築することを目的としており、その実現のために3つの主要な施策を柱としています。
2.1 全国医療情報プラットフォームの創設
「医療DX令和ビジョン2030」の中核をなすのが、「全国医療情報プラットフォーム」の創設です。これは、これまで医療機関や薬局、自治体ごとに分散して管理されていた個人の医療・介護情報を、安全なネットワーク上で連携・共有するための仕組みです。
具体的には、マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認等システムを基盤とし、電子カルテ情報、電子処方箋情報、自治体の検診情報などを集約します。これにより、患者本人の同意のもと、救急時や災害時、転院時など、どの医療機関にかかっても医師や薬剤師が過去の診療情報を正確に把握できるようになります。
結果として、重複投薬や不要な検査の削減、より迅速で的確な診断・治療につながることが期待されています。政府は、2025年度初めまでの稼働開始を目指して整備を進めています。
2.2 電子カルテ情報の標準化
全国医療情報プラットフォームを有効に機能させるためには、各医療機関が使用する電子カルテのデータ形式を統一する必要があります。現状では、電子カルテのシステムは開発したベンダーごとに仕様が異なり、医療機関同士でのスムーズな情報共有を妨げる一因となっていました。
そこで政府は、電子カルテ情報の標準化を推進しています。まずは特に重要度の高い情報から標準化を進める方針で、具体的には以下の「3文書6情報」が対象とされています。
| 標準化の対象 | 具体的な情報内容 |
|---|---|
| 3文書 | 診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書 |
| 6情報 | 傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(検体・画像)、処方情報 |
これらの情報を、国際的な医療情報交換規格である「HL7 FHIR(エイチエルセブン ファイア)」を用いて標準化します。さらに、クラウドベースで利用できる「標準型電子カルテ」の開発・普及も進め、2030年までに概ねすべての医療機関で標準化された電子カルテが導入されることを目指しています。
2.3 診療報酬改定DX
診療報酬改定は、通常2年に一度行われますが、そのたびに医療機関やシステムベンダーには大きな事務的・経済的負担が生じていました。改定内容に合わせてレセプト(診療報酬明細書)コンピュータや電子カルテの計算プログラムを改修する必要があり、その作業は複雑で多くの時間を要します。
この課題を解決するのが「診療報酬改定DX」です。この取り組みの柱は、国が診療報酬の算定ルールをプログラム化した「共通算定モジュール」を開発し、医療機関やベンダーに無償で提供することです。これにより、各ベンダーが個別に開発していた算定プログラムが共通化され、改定時のシステム改修にかかる時間とコストを大幅に削減できます。
医療機関は迅速かつ正確に改定に対応でき、ベンダーは開発負担が軽減されることで、より付加価値の高いサービスの開発にリソースを集中させることが可能になります。この共通算定モジュールは、2026年度の診療報酬改定からの本格的な導入が予定されています。
3. 医療DXがもたらす5つのメリット

医療DXの推進は、単なるデジタルツールの導入に留まらず、医療提供体制そのものを変革する可能性を秘めています。その恩恵は、医療機関で働くスタッフはもちろん、診療を受ける患者、そして社会全体に及びます。ここでは、医療DXがもたらす主要な5つのメリットを「医療機関側」「患者側」「社会全体」という3つの視点から詳しく解説します。
3.1 【医療機関側】業務効率化と働き方改革
医療現場では、診断や治療といった本来の業務以外に、カルテの記録、書類作成、情報共有など多くの付随業務が発生しています。医療DXはこれらの業務を大幅に効率化し、スタッフの負担を軽減することで、深刻化する人手不足への対策や働き方改革の実現に貢献します。
例えば、紙カルテを電子カルテに置き換えることで、情報の記録・検索・共有が瞬時に行えるようになります。手書き文字の判読に時間を費やす必要がなくなり、院内のどこからでも必要な情報にアクセスできるため、部門間の連携もスムーズになります。また、Web問診システムを導入すれば、患者が来院前にスマートフォンなどで問診を済ませられるため、受付業務の負担が減り、診察も円滑に開始できます。
さらに、診療報酬請求(レセプト)業務の自動化や、医薬品・消耗品の在庫管理システムの導入は、これまで多くの人手と時間を要していた管理業務を効率化し、スタッフがより専門性の高い業務に集中できる環境を創出します。
3.2 【医療機関側】医療の質の向上とヒューマンエラー防止
医療DXは、業務効率化だけでなく、医療の質そのものを向上させる上でも重要な役割を果たします。デジタル技術の活用により、より正確で安全な医療を提供することが可能になります。
代表的な例が、AI(人工知能)による画像診断支援です。CTやMRIなどの医用画像をAIが解析し、病変の疑いがある箇所を医師に提示することで、見落としを防ぎ、診断精度を高める効果が期待されています。また、電子カルテシステムに蓄積された患者の過去の診療情報やアレルギー情報、服薬履歴などを参照することで、重複投薬や禁忌薬の処方といったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
さらに、全国医療情報プラットフォームなどを通じて、患者の同意のもと、異なる医療機関間での情報共有が進めば、転院や救急搬送時にも患者の既往歴や治療経過を正確に把握でき、一貫性のある質の高い医療を継続的に提供できるようになります。
3.3 【患者側】待ち時間の短縮と利便性向上
患者にとって、医療DXの最も分かりやすいメリットは、利便性の向上と負担の軽減です。特に、病院での「待ち時間」は多くの患者が不満を感じる点ですが、DXによって大幅に改善されます。
スマートフォンのアプリやWebサイトから診察予約ができるシステムは、もはや当たり前になりつつあります。これにより、患者は自分の都合の良い時間を選べるだけでなく、院内での待ち時間を予測しやすくなります。来院後も、自動受付機やキャッシュレス決済システムが導入されていれば、受付や会計の列に並ぶ必要がなくなり、院内での滞在時間を大きく短縮できます。
また、オンライン診療やオンライン服薬指導の普及は、患者の利便性を飛躍的に向上させます。自宅や職場にいながら診察を受け、薬を配送してもらえるため、通院にかかる時間的・身体的負担が大きく軽減されます。
3.4 【患者側】質の高い医療へのアクセス改善
医療DXは、住んでいる場所や身体的な条件に関わらず、すべての人が質の高い医療を受けられる「医療アクセスの均てん化」にも貢献します。
オンライン診療は、離島やへき地など医療機関が少ない地域に住む人々にとって、専門医の診察を受けるための重要な手段となります。また、高齢や障害によって外出が困難な方でも、自宅で継続的な医療ケアを受けることが可能になります。これにより、これまで地理的・身体的な制約から十分な医療を受けられなかった人々の健康維持・改善が期待できます。
さらに、自身の診療情報(検査結果、画像データなど)を電子的に管理・共有しやすくなることで、セカンドオピニオンを求める際のハードルも下がります。患者自身が納得して治療法を選択するための環境が整い、より主体的で質の高い医療参加が実現します。
3.5 【社会全体】医療データの利活用と予防医療の促進
個々の医療機関や患者のレベルを超え、社会全体にも医療DXは大きなメリットをもたらします。その鍵となるのが、匿名化された医療ビッグデータの利活用です。
全国の医療機関から集約された膨大な診療データを解析することで、新たな治療法の開発や画期的な新薬の創出が加速します。また、感染症の発生動向をリアルタイムで把握し、流行予測や効果的な公衆衛生政策の立案に役立てることも可能です。これは、新興感染症への迅速な対応力強化に直結します。
個人レベルでは、ウェアラブルデバイスなどで収集した日々の健康データ(PHR: Personal Health Record)と医療機関のデータを連携させることで、個人の健康状態や生活習慣に合わせた、より効果的な予防医療や健康増進指導が実現します。これにより、国民全体の健康寿命の延伸と、将来的な医療費の抑制にもつながることが期待されています。
加えて、データをクラウド上で管理することは、災害時の事業継続計画(BCP)の観点からも重要です。万が一、医療機関が地震や水害などの被害を受けても、患者データが失われるリスクを最小限に抑え、迅速な医療提供体制の復旧を可能にします。
| 対象者 | メリットの概要 | 具体的な技術・取り組み例 |
|---|---|---|
| 医療機関 | 事務作業の削減、多職種連携の円滑化による業務効率化と働き方改革。診断・治療の精度向上と医療過誤の防止。 | 電子カルテ、Web問診、レセプトの自動化、AI画像診断支援、医薬品在庫管理システム |
| 患者 | 待ち時間の短縮、通院負担の軽減による利便性向上。地理的・身体的制約を超えた医療へのアクセス改善。 | Web予約・決済、オンライン診療・服薬指導、PHR(Personal Health Record)の活用 |
| 社会全体 | 医療データの利活用による新薬・治療法開発の促進。予防医療の推進による健康寿命の延伸と医療費の抑制。 | 全国医療情報プラットフォーム、医療ビッグデータ解析、PHRと連携した健康増進サービス |
4. 医療DXの課題とデメリット
医療DXは、医療の質の向上や業務効率化に大きく貢献する可能性を秘めていますが、その導入と推進には多くの障壁が存在します。メリットばかりに目を向けるのではなく、事前に課題とデメリットを正確に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。ここでは、医療機関が直面しやすい4つの主要な課題について詳しく解説します。
4.1 高額な導入・運用コスト
医療DXを推進する上で、最も大きな障壁となるのがコストの問題です。新しいシステムの導入には多額の初期投資が必要になるだけでなく、継続的な運用・保守にも費用が発生します。
特に、電子カルテシステムやAI診断支援システム、オンライン診療プラットフォームといった大規模なソリューションは、数百万円から数千万円規模の投資が必要になるケースも少なくありません。費用はシステムの購入費だけでなく、院内ネットワークの整備、サーバーの設置、既存システムからのデータ移行、職員へのトレーニング費用など、多岐にわたります。
また、導入後もシステムのライセンス料、保守サポート費用、定期的なアップデート費用、セキュリティ対策の更新費用といったランニングコストが継続的に発生します。特に病床数の少ない中小規模のクリニックや診療所にとっては、このコスト負担が経営を圧迫する可能性があり、費用対効果を慎重に見極める必要があります。
| 費用の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 初期導入コスト |
|
| 運用・保守コスト |
|
4.2 IT人材の不足と職員のITリテラシー
システムの導入と並行して、それを効果的に運用するための「人材」に関する課題も深刻です。DXを主導できるIT専門人材の確保と、全職員のITリテラシーの向上が不可欠となります。
医療とITの両方に精通した人材は非常に希少であり、多くの業界でDXが進む中、採用競争は激化しています。院内に情報システム部門があったとしても、日常的なトラブル対応に追われ、新たなDX戦略の立案・実行まで手が回らないケースも少なくありません。
さらに、新たに導入されたシステムを実際に利用するのは、医師や看護師、事務職員といった現場のスタッフです。多忙な業務の合間を縫って新しい操作方法を習得する必要があり、特にデジタルツールに不慣れな職員にとっては大きな負担となります。操作ミスへの不安や、従来のアナログな業務プロセスへの固執から、新しいシステムへの抵抗感が生まれ、院内での利用が浸透しないという問題も起こりがちです。
DXを成功させるには、経営層が明確なビジョンを示し、職員への丁寧な説明と継続的な教育、サポート体制を構築することが求められます。
4.3 強固なセキュリティ対策の必要性
医療情報は、個人の病歴や遺伝情報などを含む極めて機微な個人情報(PHI: 保護対象保健情報)です。そのため、医療DXを進める上では、他のどの業界よりも強固な情報セキュリティ対策が求められます。
ネットワークに接続する機器が増え、データがクラウド上で管理されるようになると、サイバー攻撃の標的となるリスクが増大します。特に近年では、医療機関を狙ったランサムウェア(身代金要求型ウイルス)攻撃が国内外で多発しており、電子カルテが使用不能になり診療停止に追い込まれるといった甚大な被害も報告されています。
外部からの攻撃だけでなく、職員の誤操作による情報漏洩や、悪意ある内部関係者によるデータの持ち出しといった内部リスクにも備えなければなりません。対策としては、ファイアウォールの設置やデータの暗号化といった技術的な対策はもちろんのこと、厚生労働省が定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した運用体制の構築、全職員を対象としたセキュリティ教育の徹底、インシデント発生時の対応計画の策定など、組織全体での取り組みが不可欠です。
4.4 システム間のデータ連携の壁
多くの医療機関では、電子カルテシステム、医事会計(レセプト)システム、放射線部門情報システム(RIS)、検査部門システム(LIS)などが、それぞれ異なるベンダーによって開発・導入されています。これらのシステムが互いに独立して稼働している「サイロ化」の状態は、医療DXを推進する上での大きな妨げとなります。
各システムでデータの形式や通信規約が標準化されていないため、システム間で情報をスムーズにやり取りすることが困難なのです。例えば、電子カルテに入力した情報を、再度レセプトシステムに入力し直すといった二重入力の手間が発生し、業務効率を損なうだけでなく、入力ミスの原因にもなります。
また、データが各システムに分散しているため、患者情報を一元的に把握したり、院内に蓄積されたデータを横断的に分析して経営改善や研究に活用したりすることができません。この課題を解決するため、国は電子カルテ情報の標準化や全国医療情報プラットフォームの創設を進めていますが、個々の医療機関レベルでは、既存システム間の連携に多大なコストと労力がかかるという現実があります。
5. 【分野別】医療DXの具体的な取り組みと活用事例

医療DXは、すでに多くの医療機関で導入が進んでおり、その活用範囲は多岐にわたります。ここでは、医療DXの具体的な取り組みを「診療・治療」「業務効率化」「患者サービス」の3つの分野に分け、それぞれの活用事例を詳しく解説します。自院の課題解決のヒントとしてご活用ください。
5.1 診療・治療におけるDX事例
医療の根幹である診療・治療の領域では、DXによって医療の質そのものを向上させる取り組みが進んでいます。医師の診断支援や、患者一人ひとりに寄り添った医療の実現に貢献する事例を見ていきましょう。
5.1.1 オンライン診療・服薬指導
オンライン診療は、スマートフォンやタブレット、PCなどを活用し、ビデオ通話を通じて医師の診察を受けられる仕組みです。患者は自宅や職場から受診できるため、通院にかかる時間的・身体的負担を大幅に軽減できます。特に、離島やへき地に住む人々や、多忙で通院が難しい人々にとって、医療へのアクセスを確保する重要な手段となっています。
また、院内での待ち時間がなくなり、他の患者との接触機会も減るため、新型コロナウイルスのような新興感染症の拡大防止にも有効です。診察後は、電子処方箋が発行され、患者が指定した薬局でオンライン服薬指導を受けた後、自宅に薬が配送されるサービスも普及しつつあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | 通院負担の軽減、医療アクセスの向上、感染症対策 |
| 活用技術 | ビデオ通話システム、電子処方箋、オンライン決済 |
| 導入事例 |
|
5.1.2 AIによる画像診断支援
CTやMRI、レントゲンといった医療画像の読影は、専門的な知識と経験を持つ医師にとっても負担の大きい業務です。AIによる画像診断支援システムは、AIが膨大な医療画像を学習し、病変の可能性がある箇所を自動で検出して医師に提示します。これにより、医師の読影をサポートし、診断の迅速化と精度向上に貢献します。
例えば、ごく初期の小さながんや、見落としやすい脳動脈瘤などをAIがマーキングすることで、医師のダブルチェックとして機能し、ヒューマンエラーの防止に繋がります。医師は最終的な判断に集中できるため、業務負担が軽減され、より多くの患者を診ることが可能になります。
5.1.3 ウェアラブルデバイスによる健康管理
スマートウォッチや活動量計などのウェアラブルデバイスは、心拍数、血圧、血中酸素濃度、睡眠時間といった日々のバイタルデータを自動で記録します。これらのデータを医療機関と連携させることで、より精度の高い健康管理や予防医療が実現します。
例えば、日常の心拍データから不整脈の兆候を早期に発見したり、血糖値センサー付きのデバイスで糖尿病患者の血糖変動をリアルタイムに把握したりすることが可能です。医師は診察時のデータだけでなく、日常生活における継続的なデータを基に、より的確な診断や生活習慣指導を行えるようになります。
5.2 業務効率化におけるDX事例
医療現場では、人手不足が深刻な課題となっています。DXは、医療従事者の事務作業や間接業務を効率化し、本来注力すべき患者ケアの時間を創出するために不可欠です。
5.2.1 電子カルテ・Web問診
電子カルテは、紙のカルテを電子データとして一元管理するシステムです。情報の検索性が格段に向上し、複数の診療科や部門間で患者情報を瞬時に共有できます。手書き文字の判読ミスを防ぎ、医療安全にも貢献します。また、保管スペースが不要になる点も大きなメリットです。
さらに、来院前に患者自身のスマートフォンやPCで問診に回答してもらう「Web問診システム」の導入も進んでいます。受付での問診票記入の手間が省け、患者の待ち時間を短縮できます。入力された内容は電子カルテに自動で反映されるため、医師や看護師のカルテ入力業務も大幅に削減されます。
5.2.2 医薬品・医療消耗品の在庫管理自動化
病院内で使用される医薬品やガーゼ、注射器などの医療消耗品の在庫管理は、非常に手間のかかる業務です。DXでは、AIによる需要予測やRFID(ICタグ)を活用して、この業務を自動化します。
AIが過去の診療実績や手術予定、季節性などを分析して最適な発注量を算出し、自動で発注を行います。これにより、欠品による診療機会の損失や、過剰在庫による医薬品の廃棄ロスを防ぎます。看護師や薬剤師は在庫管理業務から解放され、専門性の高い業務に集中できるようになります。
5.2.3 診療報酬請求(レセプト)業務の効率化
診療報酬請求(レセプト)業務は、医療機関の経営を支える重要な業務ですが、制度が複雑で専門知識が求められます。電子カルテと連携したレセプトコンピュータ(レセコン)に加え、近年ではAIを活用したレセプトチェックシステムが導入されています。
このシステムは、カルテ情報とレセプトデータを照合し、算定漏れや病名との不整合、コードの誤りなどを自動で検出します。これにより、保険者からの返戻(差し戻し)や査定(減額)を大幅に削減し、請求業務の精度と効率を向上させ、医療機関の安定した経営に貢献します。
5.3 患者サービスにおけるDX事例
患者にとっての利便性や満足度の向上も、医療DXの重要な目的です。待ち時間の短縮や手続きの簡素化は、患者の通院ストレスを軽減し、選ばれる医療機関になるための鍵となります。
5.3.1 Web予約・自動受付システム
24時間いつでもスマートフォンやPCから診療予約ができるWeb予約システムは、多くのクリニックで導入が進んでいます。患者は電話が繋がりにくい時間帯を避けて予約でき、医療機関側も電話応対業務を削減できます。
来院時には、マイナンバーカードや診察券のQRコードをかざすだけで受付が完了する自動受付機が活躍します。さらに、診察の順番が近づくとスマートフォンに通知が届く患者案内システムを導入すれば、患者は院外のカフェなどで待つことも可能になり、待合室の混雑緩和と院内感染リスクの低減に繋がります。
5.3.2 キャッシュレス決済
会計の待ち時間は、患者にとって大きなストレスの一つです。クレジットカードや電子マネー、QRコード決済といったキャッシュレス決済を導入することで、会計業務が迅速化し、患者の待ち時間を大幅に短縮できます。
現金授受がなくなるため、衛生的な上、会計スタッフの業務負担や締め作業のミスも軽減されます。最近では、診察後に会計を待たずに帰宅できる「後払いシステム」を導入する医療機関も増えており、患者満足度の向上に大きく貢献しています。
| サービス | 患者側のメリット | 医療機関側のメリット |
|---|---|---|
| Web予約・自動受付 | 24時間予約可能、待ち時間の有効活用、待合室の混雑回避 | 電話応対業務の削減、受付業務の効率化、院内感染リスクの低減 |
| キャッシュレス決済 | 会計待ち時間の短縮、現金の持ち運び不要、非接触で衛生的 | 会計業務の迅速化、現金管理業務の削減、未収金リスクの低減 |
6. 医療DX導入を成功させるための5つのステップ

医療DXの重要性を理解していても、何から手をつければよいか分からなかったり、導入が思うように進まなかったりするケースは少なくありません。しかし、体系的なステップを踏むことで、導入の成功確率を大幅に高めることができます。ここでは、医療DX導入を成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。
6.1 Step1. 目的とビジョンの明確化
医療DXを成功させるための第一歩は、「なぜDXを推進するのか」という目的(Why)と、「DXによってどのような医療機関を目指すのか」というビジョン(What)を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、導入するツールがバラバラになったり、現場の協力が得られなかったりする原因となります。
まずは、自院が抱える課題を基に、DXの目的を具体的に設定しましょう。例えば、以下のような目的が考えられます。
- スタッフの長時間労働を是正し、働きやすい環境を整備する(業務効率化)
- ヒューマンエラーを削減し、医療安全を向上させる(医療の質の向上)
- 患者の待ち時間を短縮し、満足度を高める(患者サービスの向上)
- 地域連携を強化し、シームレスな医療を提供する(地域医療への貢献)
目的を明確にしたら、次にその目的を達成した先にある「理想の姿(ビジョン)」を描きます。このビジョンは、経営層だけでなく、医師、看護師、コメディカル、事務職員など、院内のあらゆるスタッフを巻き込んで議論することが重要です。組織全体でDXの目的とビジョンを共有することで、全院的な協力体制が生まれ、DX推進の強力な土台となります。
6.2 Step2. 推進体制の構築
明確な目的とビジョンが定まったら、それを実行するための推進体制を構築します。DXは片手間で進められるものではなく、責任者と担当チームを明確に定めることが不可欠です。
院内に情報システム部門がある場合はそこが中心となることが多いですが、そうでなければ、診療科や部門を横断したプロジェクトチームを発足させましょう。リーダーには、経営的な視点を持ち、各部門を調整できる人材が適任です。
また、DXを円滑に進めるには、デジタル技術やITに関する知識を持つ人材が欠かせません。あらゆる業界でDXが進む現在、専門スキルを持つ人材を外部から採用するのは容易ではないかもしれません。
そのため、既存スタッフのITリテラシー向上のための研修を実施したり、資格取得を支援したりするなど、内部での「DX人材育成」も並行して進めることが現実的かつ効果的です。必要に応じて、外部のITベンダーやコンサルタントの専門的な知見を活用することも有効な選択肢となります。
6.3 Step3. 業務プロセスの見直しと課題の洗い出し
次に、現状の業務プロセスを可視化し、どこに課題が潜んでいるのかを徹底的に洗い出します。DXは単にITツールを導入することではなく、デジタル技術を活用して業務プロセスそのものを変革することです。
受付、問診、診療、検査、会計、レセプト請求、医薬品の在庫管理といった一連の業務フローを一つひとつ見直し、「紙媒体でのやり取りが多い」「二重入力が発生している」「情報の共有に時間がかかる」といった非効率な点やボトルネックを具体的に特定します。この作業を通じて、デジタル化すべき業務の優先順位が見えてきます。
課題を洗い出す際には、経済産業省が公開している「DX推進指標」などを活用し、自院の現状を客観的に自己診断することも役立ちます。これにより、DXの進捗状況を把握し、次にとるべきアクションを明確にすることができます。
6.4 Step4. スモールスタートでのツール選定・導入
洗い出した課題の中から、最も費用対効果が高い、あるいは現場の負担軽減に直結する領域に絞って、小規模にDXを始める「スモールスタート」が成功の鍵です。いきなり電子カルテのような大規模システムを全面的に導入しようとすると、高額なコストや現場の混乱を招くリスクがあります。まずはWeb問診や予約システム、医薬品の在庫管理など、特定の業務から着手しましょう。
スモールスタートで成功体験を積むことで、現場スタッフのDXに対する心理的なハードルが下がり、次の展開へスムーズにつなげることができます。
導入するツールを選定する際には、以下のポイントを総合的に評価することが重要です。
| 評価ポイント | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 課題解決力 | Step3で特定した課題を的確に解決できる機能があるか。 |
| 操作性 | ITに不慣れなスタッフでも直感的に操作できる、分かりやすいインターフェースか。 |
| 連携性 | 既存の電子カルテやレセコンなど、他のシステムとスムーズにデータ連携できるか。 |
| セキュリティ | 個人情報や機微な医療情報を取り扱うため、堅牢なセキュリティ対策が施されているか。 |
| コスト | 初期導入費用だけでなく、月額利用料やメンテナンス費用を含めた運用コストが予算内に収まるか。 |
| サポート体制 | 導入時の設定支援や、運用開始後のトラブル対応など、ベンダーのサポートは手厚いか。 |
複数のツールを比較検討し、デモやトライアルを活用して実際の使用感を確かめた上で、自院に最適なものを選定しましょう。
6.5 Step5. 効果測定と改善の繰り返し
ツールの導入はゴールではなく、新たなスタートです。DXの効果を最大化するためには、導入後の効果測定と継続的な改善が不可欠です。
まずは、Step1で設定した目的に対して、具体的な評価指標(KPI:重要業績評価指標)を設定します。例えば、以下のような指標が考えられます。
- 患者の平均待ち時間
- スタッフ一人あたりの残業時間
- レセプトの返戻・査定率
- Web予約の利用率
- 医薬品の廃棄ロス額
これらのKPIを定期的に測定し、「導入によってどれだけの効果があったのか」を客観的なデータで評価します。そして、思うような効果が出ていない場合はその原因を分析し、ツールの設定を見直したり、運用方法を改善したりといった対策を講じます。この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」のPDCAサイクルを粘り強く回し続けることが、医療DXを真に定着させ、その価値を最大限に引き出すことにつながります。
7. 医療DX導入に活用できる補助金・助成金
医療DXの推進には、電子カルテやオンライン診療システムなどの導入に相応のコストがかかります。しかし、国や地方自治体は医療機関のDX化を支援するため、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度を賢く活用することで、初期投資やランニングコストの負担を大幅に軽減し、DX導入のハードルを下げることが可能です。ここでは、医療DXの導入に役立つ代表的な補助金・助成金について詳しく解説します。
7.1 代表的な補助金・助成金一覧
医療DXで活用できる可能性のある、国が主体となる主要な補助金を一覧にまとめました。それぞれ目的や対象が異なるため、自院の課題や導入したいシステムに合わせて最適なものを選ぶことが重要です。
| 補助金・助成金名 | 管轄 | 主な対象経費 | ポイント |
|---|---|---|---|
| IT導入補助金 | 経済産業省 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費など | 電子カルテ、Web問診、予約システムなど幅広いITツールが対象。複数の申請枠があり、目的に応じて選択可能。 |
| 医療提供体制設備整備交付金 (オンライン資格確認関連) |
厚生労働省 | 顔認証付きカードリーダー、関連するネットワーク機器の導入費用など | オンライン資格確認や電子処方箋の導入に特化した補助。医療DXの基盤整備に必須。 |
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 経済産業省 (中小企業庁) |
設備投資、システム構築費など | 革新的なサービス開発や生産性向上を目的とした設備投資が対象。AI画像診断支援システムの開発などに活用できる可能性がある。 |
| 事業再構築補助金 | 経済産業省 (中小企業庁) |
建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費など | オンライン診療への本格参入など、思い切った事業モデルの転換を伴う大規模なDX投資に適している。 |
7.2 【国が主体】医療DXに活用できる補助金
国の各省庁が管轄する補助金は、予算規模が大きく、全国の医療機関が対象となるため、まず検討したい選択肢です。ここでは特に活用しやすい制度を掘り下げて紹介します。
7.2.1 IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的として、ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の一部を補助する制度です。病院やクリニック、歯科診療所、薬局なども対象となります。
電子カルテシステムや予約管理システム、Web問診システム、会計ソフト、セキュリティ対策ソフトなど、医療DXに直結する多くのツールが補助対象となっています。「通常枠」のほか、インボイス制度への対応を支援する「インボイス枠」、サイバー攻撃のリスク低減を目的とした「セキュリティ対策推進枠」など、複数の申請類型があるのが特徴です。自院の課題解決に合致したITツールと申請枠を選ぶことが採択の鍵となります。
7.2.2 医療提供体制設備整備交付金(オンライン資格確認導入関連)
厚生労働省が推進するオンライン資格確認は、医療DXの基盤となる重要なシステムです。この導入を促進するため、「医療情報化支援基金」による補助が行われています。
具体的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要な「顔認証付きカードリーダー」の購入費用や、システム導入にかかる工事費、ネットワーク環境の整備費用などが補助対象です。また、電子処方箋管理サービスの導入に関連する費用も補助対象となる場合があります。これからオンライン資格確認を導入する医療機関はもちろん、すでに導入済みの場合でも、システムの更新などで活用できるケースがあるため、最新の情報を確認することが推奨されます。
7.2.3 ものづくり補助金・事業再構築補助金
これらの補助金は、一般的なITツールの導入というよりも、より革新的で大規模な投資を支援する制度です。
「ものづくり補助金」は、新たなサービス開発や生産プロセスの改善に資する設備投資を支援します。例えば、独自のAI画像診断支援システムを開発・導入する、といった先進的な取り組みに活用できる可能性があります。
「事業再構築補助金」は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や事業転換を支援するものです。例えば、対面診療が中心だったクリニックが、オンライン診療を主軸とした新たな事業モデルへ転換するための大規模なシステム投資などが対象となり得ます。
7.3 【地方自治体】独自の補助金・助成金
国の制度に加えて、都道府県や市区町村が独自に医療機関向けのDX支援策を設けている場合があります。これらの補助金は、国の制度と併用できたり、より地域の実情に即した内容になっていたりすることがあります。
例えば、地域医療連携ネットワークへの参加を促すためのシステム導入補助や、小規模なクリニックを対象としたテレワーク導入支援など、多岐にわたる制度が考えられます。自院が所在する自治体のウェブサイトで「医療 DX 補助金」「IT化支援 助成金」といったキーワードで検索したり、地域の医師会や商工会議所に問い合わせたりして、活用できる制度がないか確認してみましょう。
7.4 補助金・助成金を申請する際の注意点
補助金を有効活用するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。計画的に準備を進めることが成功の秘訣です。
7.4.1 公募期間と申請スケジュール
ほとんどの補助金には、申請を受け付ける「公募期間」が定められています。期間は数週間から1ヶ月程度と短い場合が多く、気づいたときには締め切られていたというケースも少なくありません。年間を通じて複数回公募される制度もありますが、常に最新の公募情報をチェックし、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが不可欠です。
7.4.2 申請要件の適合性確認
補助金ごとに、対象となる事業者(法人格、資本金、従業員数など)や対象経費、補助率・上限額などの詳細な要件が定められています。特に、導入したいシステムやツールが補助対象として認められているか、事前に「公募要領」を熟読して確認する必要があります。不明な点は、補助金の事務局に問い合わせるなどして、確実に要件を満たしているかを確認しましょう。
7.4.3 採択後の手続きと事業実施
補助金は、原則として「後払い(精算払い)」です。つまり、申請が採択された後、まず自己資金でシステム導入などの事業を実施し、その完了後に実績報告書を提出して、初めて補助金が支払われます。そのため、一時的に費用を立て替える資金計画が必要です。また、事業完了後も、定められた期間内に事業効果に関する報告が求められる場合があります。
8. まとめ
医療DXは、超高齢社会や労働力不足といった課題を解決し、質の高い医療を将来にわたって提供するために不可欠です。医療機関の業務効率化や患者の利便性向上だけでなく、医療データ活用による予防医療の促進にも繋がります。導入コストや人材確保などの課題はありますが、国も「医療DX令和ビジョン2030」を掲げ支援を強化しています。日本の医療の未来を支える重要な基盤として、まずは自院の課題解決に向け、小さな一歩から始めてみましょう。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。
MWELT

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。