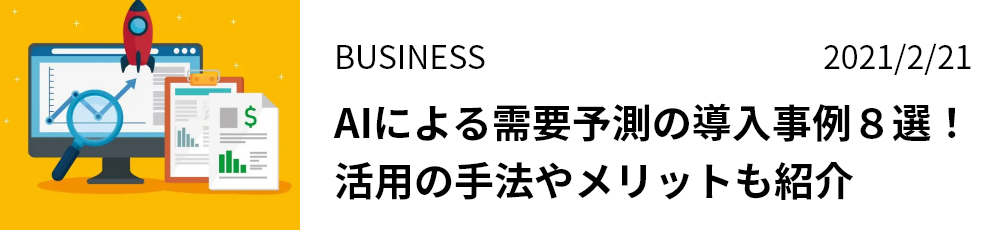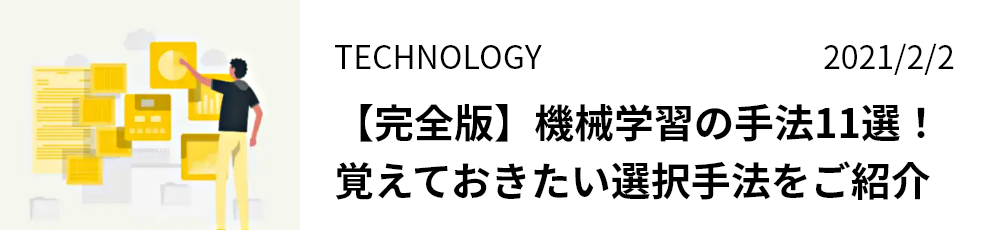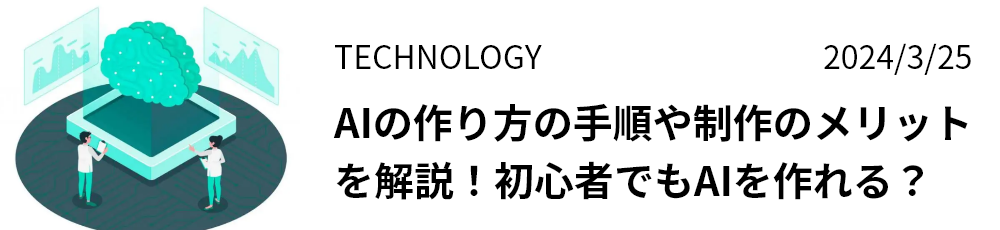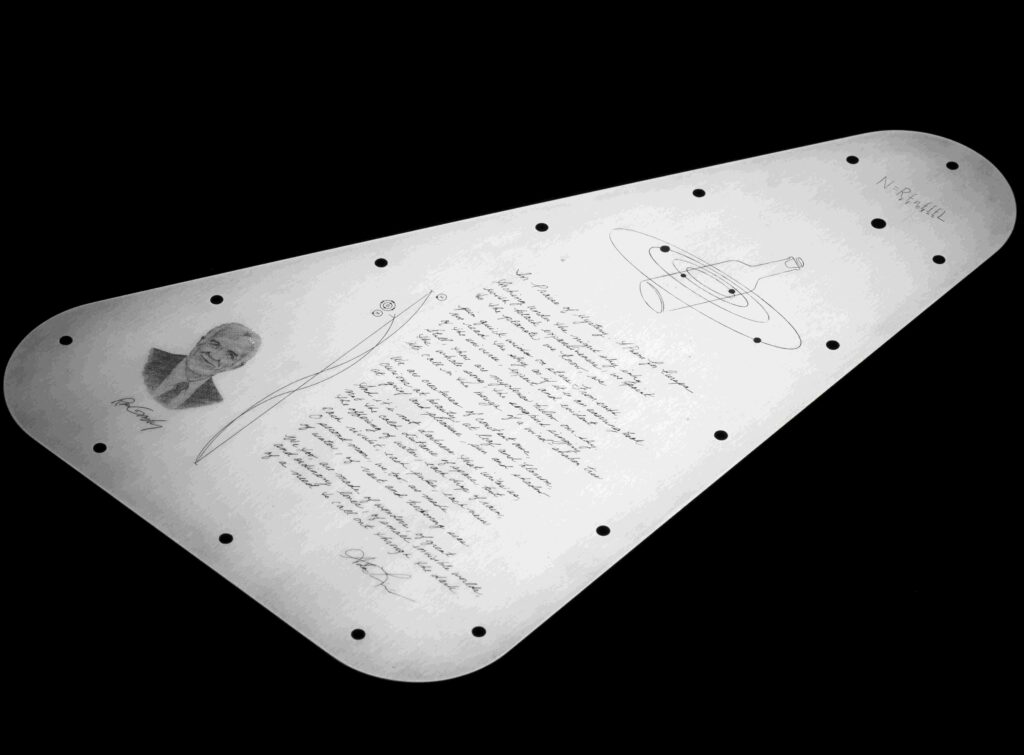SCIENCE
量子力学はなぜ生まれたのか?―前編―

目次
量子力学という学問体系は「不確定性原理」「量子もつれ」「超対称性」など摩訶不思議な多くのキーワードに彩られ、人々の興味を惹きつけてやまない。また日常で必要不可欠なスマートフォンや次世代に向けた量子コンピュータの開発など最先端科学・技術の基盤を成すものでもある。
そのため量子力学とは何か? といった趣旨の書籍・記事も多く存在するものの、どうにも難解であることが常である。「光は波であり同時に粒子でもある」などと言われたところでそんなものは私たちの身近な感覚からはかけ離れており、興味深くも難解なキーワードから浮かび上がるテクスチャーはまるで言葉や概念のイリュージョンのようだ。
だからと言って量子力学の専門書を紐解き、シュレーディンガー方程式の解法や量子場の理論・量子情報といった専門知識を高い解像度で学ぶのは専門家・科学者という達人の域であり、さらに難しい。
量子力学の「魅力的だがよくわからない難しいもの」というテクスチャーからどうしたら抜け出すことができるだろうか? 筆者は、量子力学とは何か? ではなく「なぜ量子力学が必要か」に注目をして、テクスチャーを超えた量子力学の存在感を感じてもらうことが大事なのではないかと考えている。なぜ? という理由・論理を究めていくのが窮理学すなわち自然科学の本質だからだ。
そこで、まだ量子力学という学問体系が成立する前、19世紀後半から20世紀前半にかけて科学者たちが何を見つけ、何に不思議さを感じ、そして「なぜ」量子力学が生まれたのかを本稿ではざっくりと紹介したい。
自然界に溢れる光

量子力学は私たちの生身の視覚では到底認知できない、10-9 m(10億分の1メートル)という極微の自然現象を理解するための学問体系である。そうなると当然浮かぶのが「目に見えないのにかつての人はなぜ極微の自然を認識することができたのか?」という疑問である。還元論的な立場に経てば、世界の解像度を高めていくことは自然な研究アプローチだが、光学顕微鏡などでも視覚的に観察できないような極微の現象は、読者である皆さんと同様に当時の最先端科学者の間でも到底容易には認識できるものではなかった。
人間の認知能力の外側にある極微の世界と私たちを結びつけたもの、それは「光」であった。電磁気学に関する数多くの研究、そしてジェームズ・クラーク・マクスウェルによる電磁気学の体系化に伴い「光とは空間を伝播する電磁気の波である」などと19世紀半ばにはその理解は随分と深まっていた。光は星々の煌めきであり、太陽の恵みでもあり、自然界に満ち溢れている。
光を手がかりに自然界をこれまでとは違った視点で眺めてみようという試みに至るのも頷けるだろう。マクスウェルの理論は極めて美しく多くの事柄を統一的に理解することができ、光にまつわる自然現象はこの理論をベースに全て説明できるだろう、と研究者たちは信じて疑わなかった。
失われた光の謎

しかし研究者たちは、どうしてもマクスウェルの理論では説明できない自然現象に気づいてしまった。
そのひとつが、ヨゼフ・フォン・フラウンホーファーが発見した「黒線」である。フラウンホーファーは高性能な光学ガラスを製造し、1814年に太陽からの恵みたる日光を精度よく分光、つまり虹のように太陽からの光を様々な色の光の成分に分けて観察した。
その結果「光のグラデーションの帯は実は所々黒くかけている」ことを発見した。太陽からの白色光は幅広い色の光が満遍なく含まれているのではなく、バーコードのように等間隔ではない箇所で、特定の波長の光が失われていたのだ。完璧のように見えたマクスウェルの理論では、このフラウンホーファーが観測した「失われた光」の存在を示す黒線の詳細を説明することができなかった。
一方で、水素原子などの物質から「放たれた光」は、失われた光の逆で、バーコードの白と黒をひっくり返したように、特定の色の光だけが飛び飛びで観測された。これもマクスウェルの理論では説明できない。
例えばネオンガスに電気を流すと光輝くが、夜の繁華街をかつて彩ったネオンサインの輝きは赤紫に色づいていたことを思い出してほしい。私たちの生活を支えるLED光源も、世に出始めた頃は赤色・緑色という特定の色の光を放っていたのを想像してほしい。太陽光から失われた特定の色の光、そして物質に電気を流すと特定の色の光が放たれることこそ、物理学の理論体系に「量子(quantum)」というアイデアを必要に迫った自然現象なのだ。
なんだかわからないが必要だった量子性

日本語で「量子」と訳されるquantumはラテン語である”quantus”に由来し、19世紀の科学界では”十分な量”というニュアンスで使われていたらしい。1900年12月14日にマックス・プランクが発表した熱放射現象に関する論文の中で初めて、現在のそれに近い意味で量子という言葉が用いられた。
トーマス・エジソンがもたらした白熱電球の原理にもあるように、物質は熱することでも光を放つことができる。この熱放射現象は19世紀の産業革命を推し進める上でも重要な性質であった。例えば製鉄所でドロドロに溶けた鉄が赤白く光っている様を映像で観たことがあるかもしれない。またガラス加工では、炉の正確な温度を知ることが繊細な温度管理につながる。温度と光の関係は、産業ニーズとも直結した、当時最先端の研究課題であった。
この課題に取り組んでいたマックス・プランクは、熱放射現象に関する自らの理論の中で、光は世界と「十分な量の」小包(パケット)でしかエネルギーをやり取りできないものだと仮定・表現した。世界を構成するモノたちはエネルギーをやり取りすることでその形態や運動を変化させる。どんなにわずかな水の流れでも水車を動かすエネルギーを与えるし、燃料の量を微調整すれば火力も制御できる。
しかし、彼の仮説はこの我々がエネルギーに対してもつこれらの感覚と矛盾するものだった。スロットマシーンが特定のコインを与えることでしか動作せず、また同じコインしか吐き出すことができないように、機械でもない世界も、小さいにせよ確かに有限な量(コイン/もしくは量子)のエネルギーしか光とはやり取りすることができないと仮定したのだ。水がある勢いに達するまでなんの仕掛けもない水車を動かすことができないと言っているようなものだった。
この熱放射現象におけるエネルギーの取り扱いは、どこまでも細かく調整できる「連続」というアイザック・ニュートン以来の概念に基づいた物理学の範疇では決して正当化することができない大胆な仮説であったが、実験事実を完璧に説明することができた。しかし、このような主張をしたマックス・プランク自体もこれは止むを得ない急場凌ぎの対処であり、量子をできる限り排除する理論はないものかと画策を続けたと言われている。それほどまでに何だかわからない、常識の外側にあるアイデアだったのだ。
魔法から確かな存在へ

光と物質の関係を詳細に紐解くには「量子」という不思議な概念を理論に組み込まざるを得なかった。これが「なぜ量子力学が生まれたのか?」に対する回答のひとつである。
量子とは何かを知る以前に、量子という概念がないとうまく現象と理論の整合性が取れなかったのだ。生まれた当初の量子とは、物語に登場する魔法のように都合はいいが現実味も根拠もない、迷信のようなモノだった。
量子という概念は疑われつつも検証が続けられ、その結果、単なる迷信ではなく確かに自然界に組み込まれた要素であると、今では多くの研究者が確信している。プランクの考えを発展・応用したのがアルバート・アインシュタインであり、彼が1905年に発表した金属にあるエネルギー以上の光を照射するとその表面から電子が飛び出す「光電効果」と呼ばれる現象を説明する理論へと引き継がれ、1922年のノーベル賞受賞につながった。それでもなお2022年のノーベル賞が量子性に関する基礎研究であったように、研究者たちは「量子とは何か?」を探求し続けている。
*後編へ続く
参考文献
・フラウンホーファーの光学ガラスと太陽スペクトル暗線:https://www.jstage.jst.go.jp/article/pesj/54/3/54_KJ00005898259/_pdf/-char/ja
・素粒子物理学をつくった人びと(上)(下), ロバート・P・クリース, チャールズ・C・マン, (訳: 鎮目 恭夫, 林 一, 小原 洋二, 岡村 浩)ハヤカワ・ノンフィクション文庫, 早川書房
・EMANの物理学, プランクの理論:https://eman-physics.net/statistic/planck.html
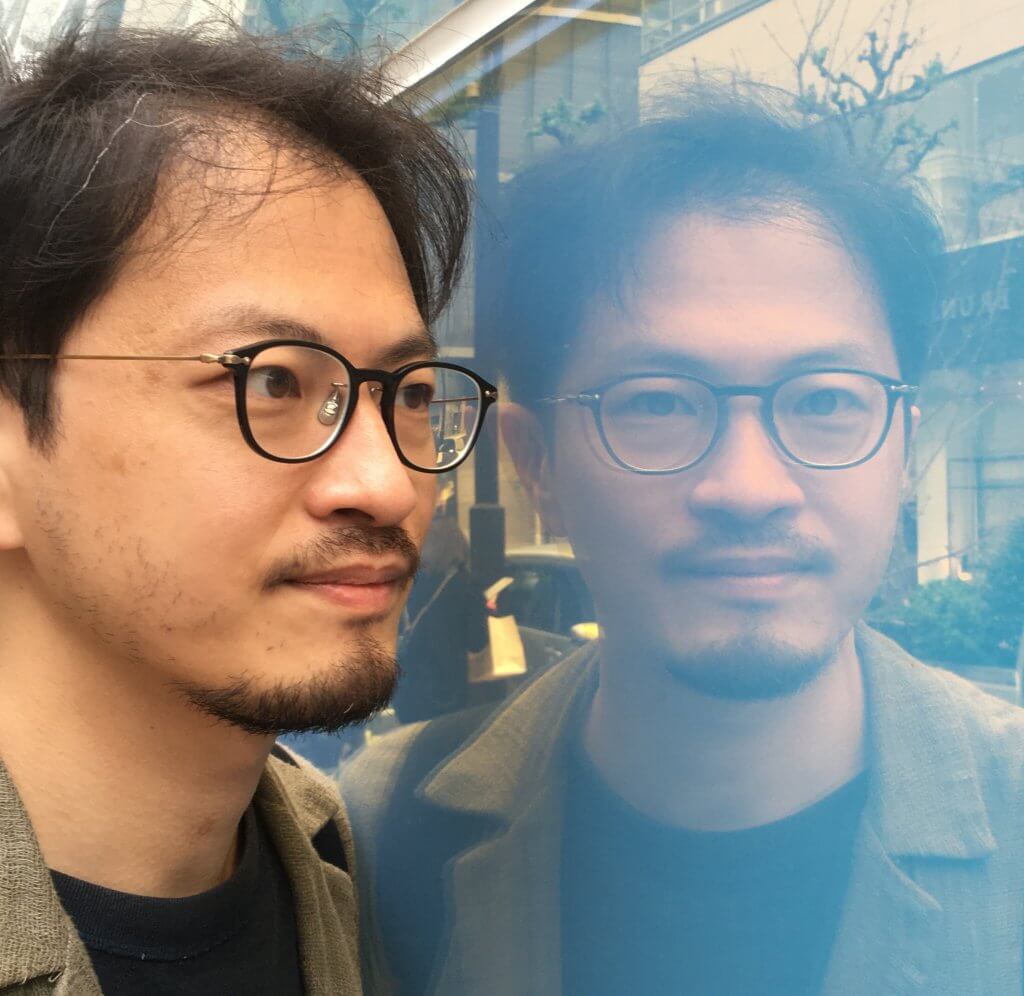
安藤 康伸
ライター
博士(理学)。国立研究開発法人にて機械学習や計算シミュレーションを材料開発に活用する研究に従事。企業向け技術セミナーや学生向け出張授業に加え,趣味でサルサダンス・ミュージカル・インプロなどのステージにも立つ。好きなお酒は無冠帝・ポルフィディオ・アネホ若しくはブッカーズ。