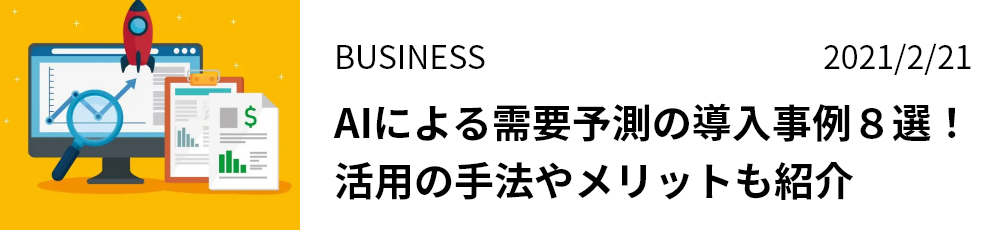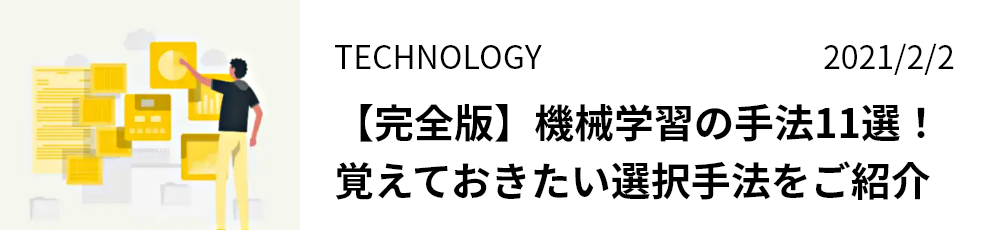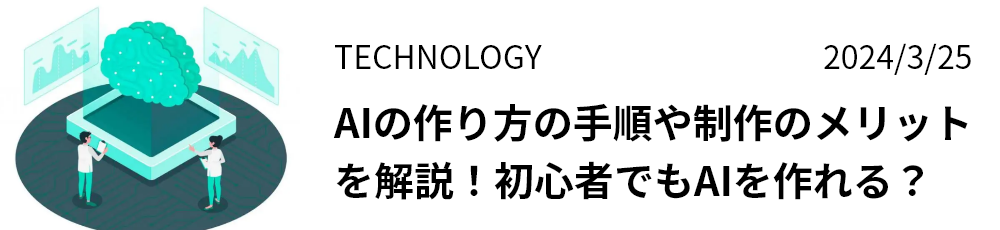CULTURE
“今ここ”に集中して、人生が変わる。奥深き「陶芸」と「マインドフルネス」の関係

目次
ろくろのモーターが唸る音。手に伝わる、ひんやりとした土の感触。ほんの一瞬、気を逸らしただけで、蕎麦猪口の飲み口は無情にも大きく歪んでしまう。試行錯誤を繰り返しているうちに、気づけば授業の2時間はあっという間に過ぎる──。
「効率化」や「最適化」ばかりがもてはやされる現代。スマホをひと撫ですれば、あらゆる欲求が即座に満たされるこの時代に、あえて手間のかかることに没頭することには、どんな意味があるのだろうか。
著者にとって、その答えは陶芸にあった。ろくろに向かうと、時間の感覚が消え去り、作業を終えたあとには脳がスッキリと冴え渡る。まるで、マインドフルネスで得られる爽快感に似た心地よさが訪れるのだ。
今回は、陶芸がなぜこんなにも心を整えてくれるのかを、マインドフルネスとの共通点を手がかりに紐解いていこう。
陶芸を手放した私が、再び土を捏ねるまで
デンマークのフォルケホイスコーレに留学中、陶芸は「私には向いていない」と結論づけたはずだった。
著者が留学した学校には陶芸のクラスがあり、本格的に学べる環境が整っていた。ほとんどの生徒が受講を希望するほどの人気で、教室はいつも生徒でごった返していた。
最初に取り組んだのは、粘土を板状にのばして成形する技法「たたら」。筒状の作品を作ってみるも、表面はボコボコで、まったく綺麗にできない。その後も、棒状の粘土を積み上げて形を作る「手びねり」でマグカップに挑戦したが、どうしても納得のいく仕上がりにはならなかった。
やればやるほど不恰好になっていくジレンマを抱き続けた結果、クラスを途中で辞めた。表向きの理由は別に考えたものの、正直なところ、完璧主義のきらいがある著者にとって陶芸は、ただストレスが溜まるだけだった。
しかし、昨年ヨーロッパを訪れたとき、どこへ行っても、現地の作家が作った陶芸作品に手を伸ばし、微笑んでいる自分がいることにふと気づく。「私は、陶芸を諦めきれていない」。
ネットで近くの陶芸教室を探してみると、運がいいことに、自宅から車で10分のところに本格的な窯を見つけた。逃げるように辞めた陶芸を、私はもう一度始めることにした。
一挙手一投足が出来上がりを左右する、究極のアート

陶芸といっても、学ぶ地域によって考え方やスタイルはまったく異なる。日本では、縄文時代に食料の保存や調理などのために粘土を焼いて器を作る技術が発展し、独自の進化を遂げてきた。一方、世界ではさらに早い時期から陶芸文化が芽生え、中国の黄河流域の彩陶文化や、メソポタミア、エジプトなどでも、それぞれ独自の陶芸文化が育まれていった。
陶芸を日本で再び学ぶ中で、日々気づかされるのは、究極のアートであるということ。先生のお手本を真似てみても、うまくいかない。ろくろやたたら、手びねり……どの技法を試しても、同じ形を作れるようになるには気が遠くなるほどの訓練が必要だと、痛感させられる。
陶芸は土に始まり、一つ一つの動作、力の加減、気候など、あらゆる条件がそろって生み出される産物だ。ちょっと力を入れただけでも焼き上がると歪んでしまうし、思った形・色になるかは、窯から出してみるまでわからない。長年、陶芸を続ける人たちが何気なくこなす動作も、実は経験と試行錯誤の積み重ねなのだと気づかされる。
ただし、技術だけがあればいいのではない。良い土を選ぶ目を養い、触れただけで水加減を見極める感覚も欠かせない。どれだけ腕が良くても、土の質や水の管理が悪ければ、良い作品にはならない。「素材が良くて初めて、技術が生きる」という価値観が、陶芸には根付いているのだ。
陶芸がもたらすマインドフルなフロー体験

陶芸のアートとしての背景にも味わい深さを感じるが、私が毎週、陶芸教室を心待ちにする理由は他にもある。陶芸後のマインドフルネスに似たすっきりとした爽快感が、忙しい日常から距離を置くための心の拠り所になっている。
マインドフルネスとは、簡単に言うと「ただ今に意識を向け、それに気づく」 こと。ぼーっと考え事をしたり、過去の後悔や未来の不安に引きずられるのではなく、“今この瞬間”に湧き上がる感情や思考に気がついている状態だ。
たとえば、ろくろの上にある茶碗に指を添えて、土の感触と指先の抵抗に全神経を注ぎ、「私は今指先に集中している」と気がつく瞬間。そうした“今ここ”に集中する状態は、ストレス軽減やレジリエンス(回復力)の向上など、さまざまな効果が多くの研究で示されている。
マインドフルな瞬間が、陶芸など制作を行う過程で得られやすいことは研究でも明らかになっている。アート制作がどのようにマインドフルネスを促進し、精神的な健康を向上させるか調べた研究(※1)では、アート制作は、自然に“今ここ”への集中を引き出し、フロー体験、つまり時間が経つのも忘れて夢中になる心理状態を生み出すことで、過去や未来への心配を和らげ、リラクゼーションを促進するとされる。
加えて、同研究では、芸術制作後にいわゆるストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが有意に低下した。
他にも、不安や抑うつ状態を抱える人を対象に、マインドフルネスを取り入れたアートセラピー(MBAT)が与える影響を調べた研究(※2)では、血圧や脈拍、呼吸の状態が安定し、リラックス感の向上も確認されている。
デジタルの対極「自然とのつながり」が生み出す気づき

情報が溢れる現代では、膨大な情報を処理し続けることで、脳疲労が引き起こされやすくなる。だからこそ、デジタルから距離を置き、土を通して自然とのつながりを取り戻す作業に、本能的に惹かれたのかもしれない。
陶芸をしていると、過去や未来を考える余裕なんて一切ない。もし意識が今から離れれば、その迷いはそのまま作品に現れてしまう。でも、その緊張感が、余計な雑念を追い払う手助けとなり、“今ここ”に集中させてくれるのだ。
さらに、忙しい毎日から離れ、デジタルの対極である“土”に触れることで、自分が自然の一部であることを思い出すきっかけにもなった。
普段は当たり前すぎて意識しないが、私たちは日常的に土から多くの恩恵を受けている。陶芸を通してその事実に改めて気づくことで、「自然からの恵みを無駄にしない」という感覚だけでなく、土からものが生まれ、役目を終えたら自然へと戻っていく循環も意識するようになった。地球に生きる者としての責任を感じると同時に、土があるからこそ生かされているのだと、自然への感謝が湧いてくる。
これらの気づきの中で、かつては許せなかった歪みや凹凸は、「自然と私が織りなす味」として愛おしく思えるようになっている。
陶芸という古の時代に生まれた技術が、AIを操る現代人の心を癒す──。ここ数年で、飛躍的にテクノロジーが暮らしに溶け込んできているからこそ、古くからの知恵や技術がもたらす効能が再認識され始めている。実際に陶芸にも、連綿と紡がれてきた歴史があり、今がある。これからの時代は、古きをたずね、そこから新しい気づきや創造を生み出す、温故創新の姿勢がより注目されるかもしれない。
参考文献
※1 Giraldi, L., & Walker, A. (2016). The Role of Mindfulness in Artistic Expression: How Creative Processes Enhance Mental Well-being. Frontiers in Psychology, 7, 761.
※2 Tang, C., & Zhao, Y. (2023). Art, Mindfulness, and the Neurobiology of Flow States: A Study on Creative Immersion and Mental Health Benefits. arXiv preprint, arXiv:2308.12601.
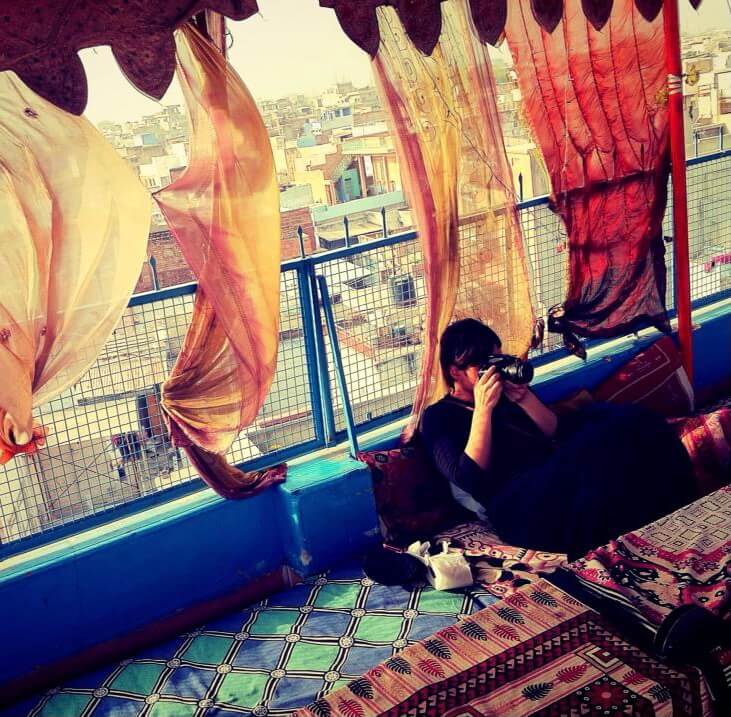
Ayaka Toba
編集者・ライター
新聞記者、雑誌編集者を経て、フリーの編集者・ライターとして活動。北欧の持続可能性を学ぶため、デンマークのフォルケホイスコーレに留学し、タイでPermaculture Design Certificateを取得。サステナブルな生き方や気候変動に関するトピックスに強い関心がある。