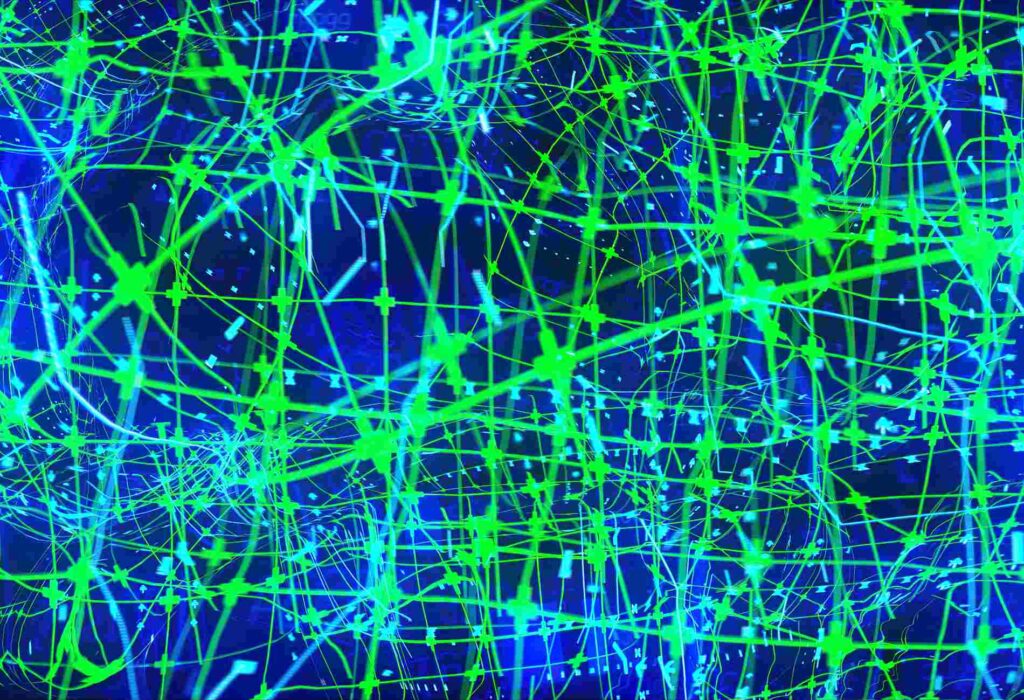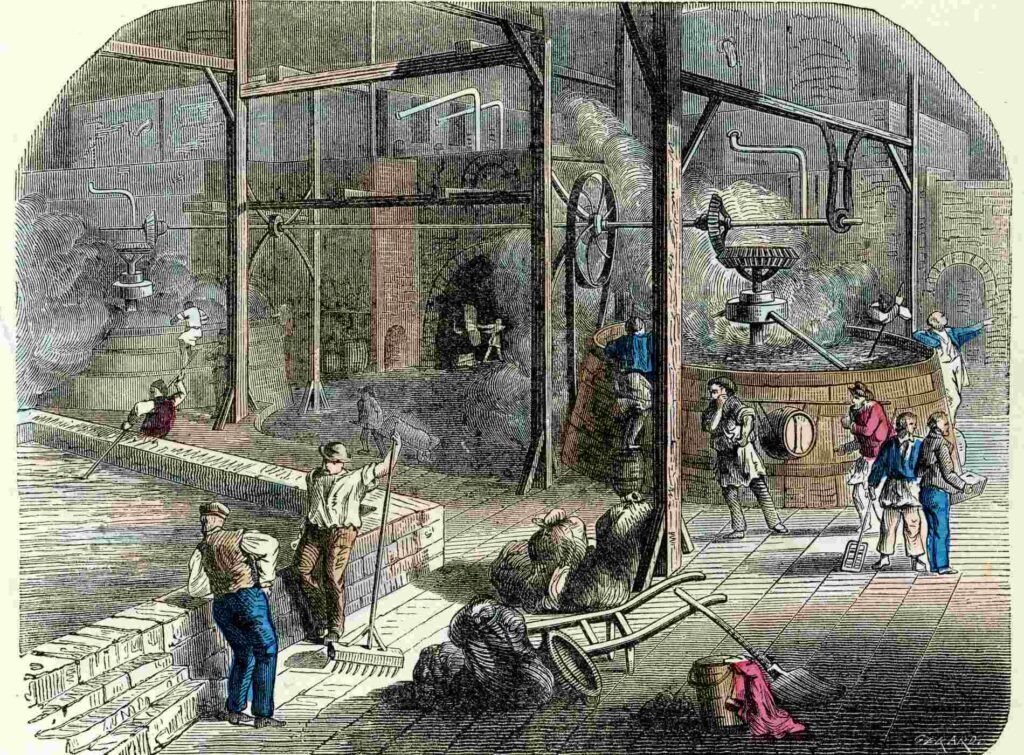BUSINESS
お金のルーツをたどれば “負い目”に行き着く

目次
「自分が欲しいものを持っている相手が欲しがるものを、自分が持っているとは限らない。お金が生まれたのは、そんな物々交換の不便を解消するためだ」というストーリーを聞いたことがないだろうか。「欲望の二重の一致」と呼ばれるこの概念は、長らく経済学の通説とされてきたが、歴史的な事実とは異なるとの見解が近年有力になってきた。本稿では、異議を唱えた論者の代表格である人類学者、デヴィッド・グレーバー(1961-2020)の著書『負債論——貨幣と暴力の5000年』(以下「同書」)をもとに、この再検討が意味するものを考えたい。
「欲望の二重の一致」論は、なぜ通説だったのか
高度に都市化・分業化・産業化した社会で暮らし、交換という習慣に馴染んでいる私たちにとって「欲望の二重の一致は難しい」という指摘は、どこか切実に感じられる。しかし貨幣経済が未発達だった時代には、価値の等しいものを同時に与え合う物々交換そのものが、あまり一般的な行為ではなかったというのがグレーバーの説明だ。同書では、近隣の部族と交易する先住民の例などを引きつつ、物々交換が本来、いかにイレギュラーな取引形態であるかが強調される。
「潜在的には敵どうしである 一歩まちがえれば戦争状態に転じるような人間のあいだで、物々交換はおこなわれる。(中略)どちらかの側が相手にごまかされたとおもい込んだとき、この関係はただちに現実の戦闘に転化する」(同書から引用)
つまり貨幣を「欲望の二重の一致が困難なときでも交換を成立させられる道具」と捉える見解(18世紀のアダム・スミス、さらに遡ると紀元前4世紀のアリストテレス)は、物々交換が成り立つ前提条件を掘り下げず、ある見方に限れば辻褄が合うよう単純化された説明に過ぎないといえる。もっともこうした単純化には、しかるべき理由と、大きなメリットがあったようだ。
発生原因である個別の人間関係から切り離すことで、経済活動はそれだけを独立させて、定量的に扱うことが可能になった。数字だけで完結させられることは経済学の発展につながったし、学者以外の人々にとっても、手にするお金が数値化された価値にすぎず、いかなる“色”も付いていないことは便利極まりない。なぜなら金額が合いさえすれば、いつでも・どこでも・何にでも後腐れなく使えるからで、この自由さこそが近代の経済発展の原動力だったともいえる。
さらにこうした交換の原理は、国家の存在と税金の徴収を正当化する根拠にもなっている。というのも、“お金に色が付いていない”メリットを生かすべく、何でもスムーズに取引できる環境を維持するには「受け取り拒否を認めない」という強制が求められる。こうした強制力は究極的には武力で裏付ける以外になく、その維持には必ずコストがかかるためだ。
貨幣を成り立たせたのは「負債」である

グレーバーも示唆するように、貨幣の成り立ちに関する説明はこれまで、意識的に単純化されてきた部分が大きいのだろう。概念として扱いやすい貨幣の流通は、より多くの人々に便利な生活をもたらしたし、日常のほとんどを埋め尽くすに至った交換の概念は、(仮にそれが建前に過ぎなくても)当事者の対等な関係を前提とする点で行儀がよく、慣れてしまえば心地よいものである。
とはいえ、豊かさへの貢献をどれほど肯定しても、「等価物の同時交換」をあらゆる経済活動の基礎に置く説明は一面的で、かなり歪と言わざるをえない。単純さゆえの通りの良さを野放しにすれば拝金主義を招くし、「借りたら返すのが当たり前」という常識は「理由はどうあれ返さない奴が悪い」と、個別事情や構造的問題を抜きに責めたてる不寛容と紙一重だ。さらに、交換が前提とする対等な関係から外れた経済活動(例えば人身売買)を理解できなければ、大きな不正義を見落とすことにもなるだろう。
では分業と交換がここまで発達する前から、貨幣を根本で成り立たせてきたものは何だったか。それは心理的な「負債」だというのが、人類学的な研究成果を踏まえた同書の説明だ。
“負い目”は、いかにして“お金”になったか
貨幣を成り立たせる負債の具体例としてグレーバーは、贈与を受けたとき相手に感じる負い目や、リーダー格を維持するために必要な気前よさ、さらに取り返しのつかない損害を与えた相手への償いなどを挙げる。
ざっくり言えば「貨幣が成り立つベースには、対人関係の均衡を保とうとする自然な心理がある」ということだが、これは今日の生活感覚からみても納得のいく説明だろう。
「だれかになにかを負っている[借りがある]という感覚、それと負債との違いとは、正確にいえば、なんであろうか? 答えは単純だ。貨幣である。負債と義務の違いは、負債が厳密に数量化できることである」(同書から引用)
取り返しのつかない損害に対して償いを命じる権力者は、賠償が損害と釣り合うか判断しなければならない。ここであらゆる財は、価値の定量化にさらされる。また、足りない生活必需品を補い合う相互扶助は、交易などを通じて欲望の対象が多様化するにつれ、等価物の交換へと変容していったとみられるが、そこでも同時交換が必須というわけではなく、個別の信頼関係をベースに一定の時間軸の中で釣り合いを取ることが多かったと同書は説く(「お互い様」という日本語からも容易に想像できる関係だろう)。
では、今日使われるような「お金」は、そこからどのようにして生まれたのか。多くの留保を残しつつ、同書が示唆したストーリーを強引にまとめれば、およそ次のようになるだろう。
「負債を証明した借用書は、それを誰が持ってきても決済する約束であれば、借り手以外の誰かに対する支払いとして貸し手が手放しても全員の辻褄が合う。この方法は特に商人にとって便利だったため普及し、個別の人間関係を離れて信用が流通するようになった(人間関係でカバーできないリスクを上乗せする必要から利息が生まれたという説明が可能)。今日のお金に直接つながる際立った出来事は、こうした抽象的な信用取引が十分定着した紀元前6~7世紀の中国・メソポタミア・トルコ西部で、武力を背景に持つ支配者が取引の媒体として自ら発行する硬貨を使うよう求めたことである」
損得への囚われから離れられるか
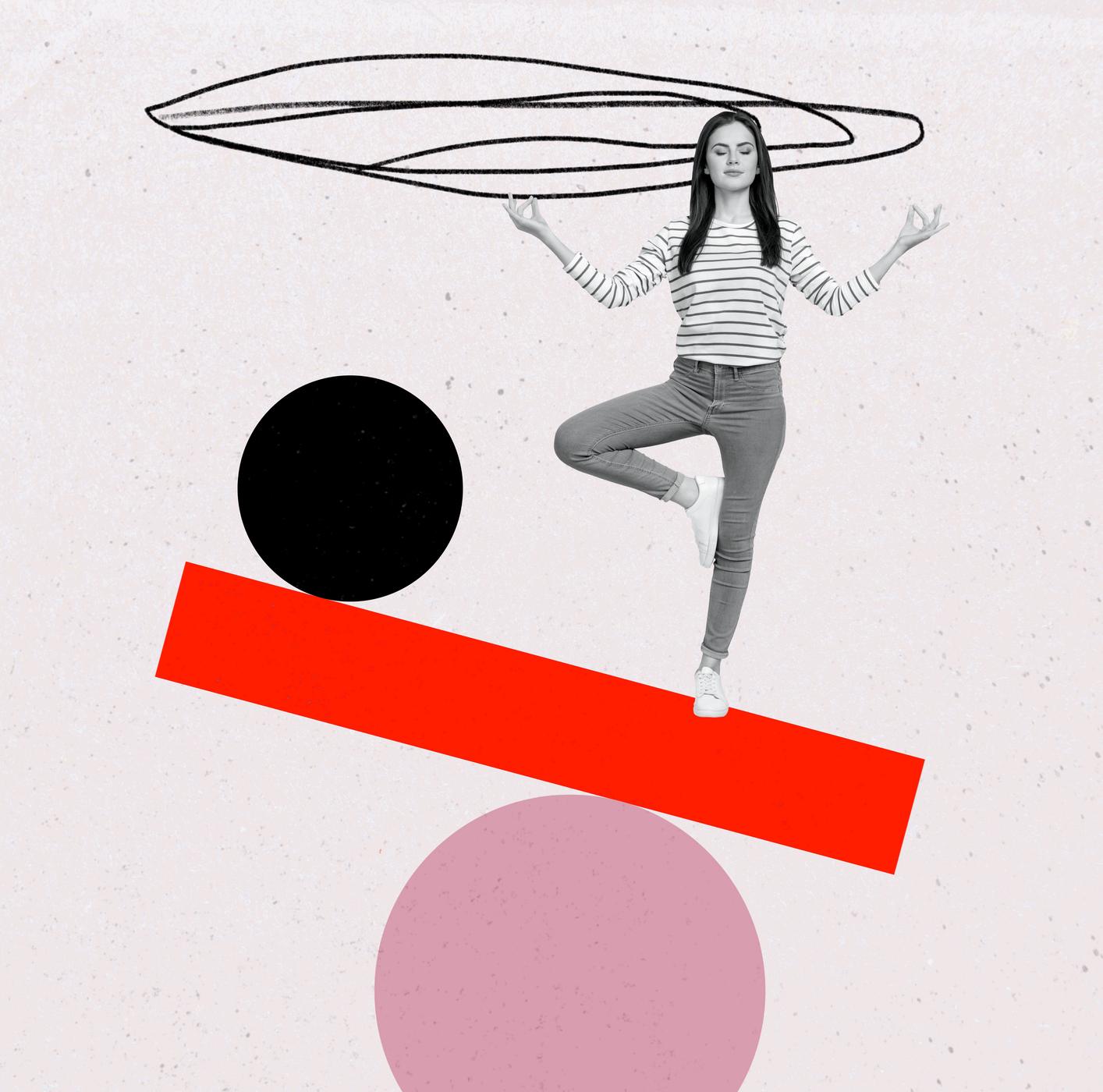
従来の通説に反し、経済活動の原理が「欲望の二重の一致」より深いところにあるならば、この貨幣経済万能の世界にあっても、そのデメリットをかわす何らかの方法が見つかるはずだ。
細かな損得計算に縛られがちな、等価物の交換「ではない」関係性として、同書はヒエラルキー(優位者から劣位者への一方的な贈与)やコミュニズム(能力に応じた貢献と、必要に応じた付与)を挙げているが、より形式的なルールを理屈で考えただけでも、ざっと以下のようなバリエーションが思いつく。
・同時交換をしない。清算されていない貸し借りの関係を、絶えず残しておく
・直接お金を介在させない。会って話す、自然に親しむといった体験を共にする
・互酬関係にとらわれない。与えっぱなし、もらいっぱなしの関係があってもよい
・損得の感覚から離れる。あげた、もらった、その値打ちはなどと一々考えない
ただ想像すれば分かるとおり、損得への囚われから離れるこうした関係性は、すでに何らかの仲間感覚やメンバーシップを共有している間柄でこそ成り立つものだ。交換の「主体」どころか「対象物」として扱われる奴隷が、あらゆる人間関係を奪われた者の身分であることをグレーバーが強調するのも、そのためだろう。
キャッシュレス化・サブスク化が進む近年の消費社会は、金銭換算された価値の交換が日常の隅々にまで及んでいる事実を意識させず、いっそう見えにくくしている。一見親切なシステムに誘われるまま、“あちらの論理”に取り込まれてしまう危険と、絶えず隣り合わせの時代ともいえるだろう。私たち自身にとって真に価値ある生活を送れるかどうかは、損得抜きでいられる間柄を誰と・どう築くかにかかっているのかもしれない。
参考文献
Graeber, David. 2011.“DEBT:THE FIRST 5,000 YEARS” New York: Melville House Publishing(高祖岩三郎・佐々木夏子 訳『負債論——貨幣と暴力の5000年』以文社 ,2016)

相馬 大輔
ライター
地方紙・業界紙での記者経験を経て、2016年にフリーライターとして独立。現在、上場企業経営者や実務家へのインタビュー、ITツール導入事例紹介など、聞いて字にまとめる業務全般に従事。社会見学レポートのよい書き手でありたい。